-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
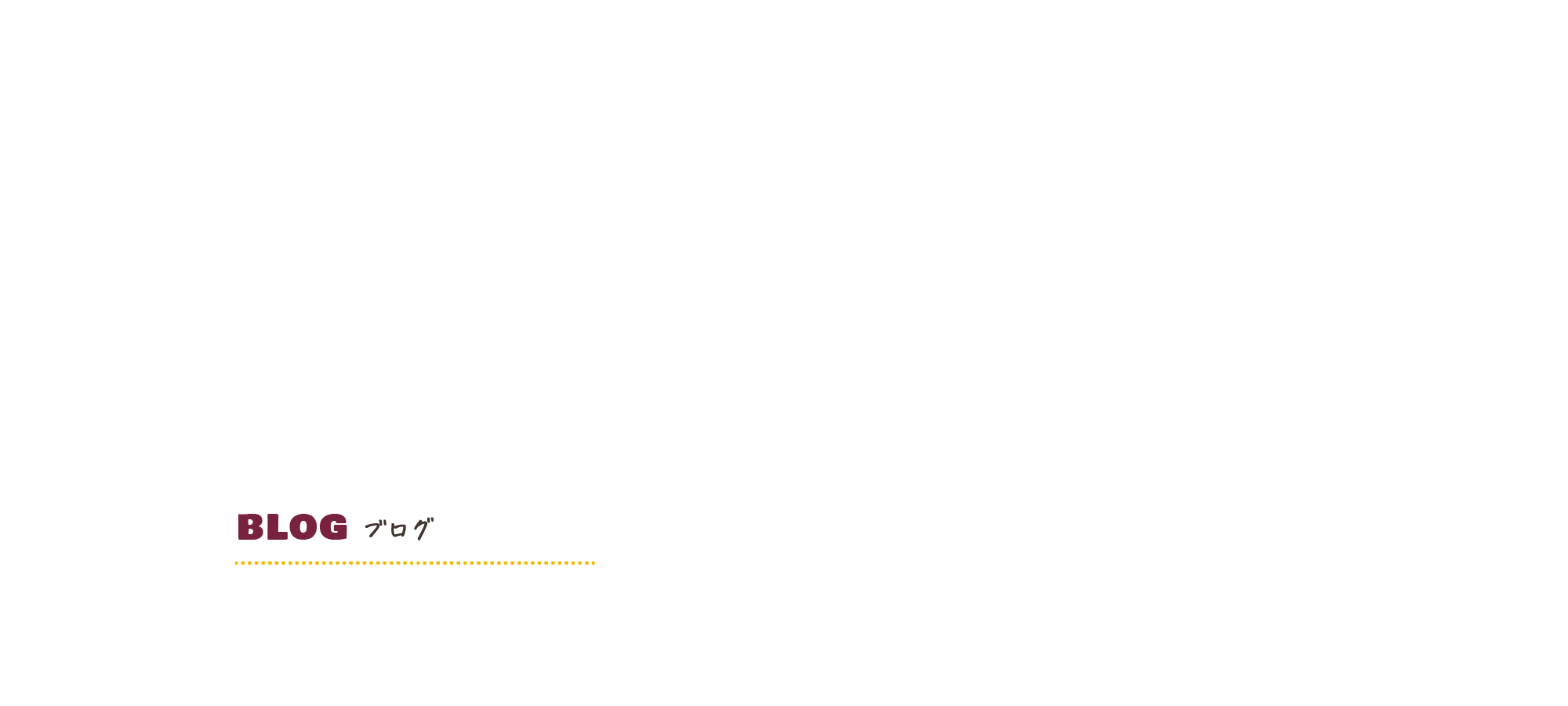
こんにちは。マフです。
前回「さつまいもって、そもそも主食?おかず?おやつ?」
という問題に対し、
農林水産省のHPにも記載されている「基礎食品」という分類から、
「主食である」と答えが出そうになりました。
しかしそれだけでは、まだまだ断定材料にはなりません。
というわけで、そもそもの「さつまいも」という言葉について、調べてみます。
学研の国語辞典によると【蔓性の作物。別名カンショ。】
さらに説明分には【第二次世界大戦中はわが国の重要な食料となった】
とありました。
そうなんです、かつての戦時中では、
「農林一号」の名で食糧不足解消のために大量生産され、
来る日も来る日も食卓に上がっていたそうです。
明治・大正生まれの人たちにとっては、
紛れもなく「主食」という位置付けにあったのだと思います。
ただ、その時の反動があってか、わたしがずっといっしょに暮らしていた祖父祖母は、
戦中の経験からか「さつまいもを主食として食べたくない」「たまのおかずくらいなら…」
という考えを持っていて、それが我が家の食卓に反映されていたため、
わたしの印象では「さつまいもはおかず」という感じだったのでした。
なので、もしかしたらそういった影響を受けた家庭の食卓も多かったから、
さつまいもが主食かおかずかおやつかと、意見が分かれるのかもしれませんね。
しかしどうあれ、大別されるならば、上記の事情もあって、
どうやら「主食」という枠に入れるのが最も適当のようです。
そもそも「さつまいも」が日本全国に広まったのは、
江戸時代に徳川吉宗の命を受けた蘭学者・青木昆陽が、
続く飢饉による食糧難を打開するための救荒作物として採用したのがきっかけです。
(もちろんそれ以前にも「甘藷栽培」の記録はありますが、
幕府による本格的な普及と試作は、この時の、彼が担当者として記録されたところからによります)
救荒作物とは、すなわち「主食足りうる代用品」であり、ご飯の代わりとなるものです。
よって、結論としては、
「さつまいもは主食である」
と断定してしまっても、決して間違いとは言えないでしょう。
では「さつまいもはおやつ?」という考えはどこからきているのか。
それを次回、最後におまけとして取り上げたいと思います。
さつまいも問題③に続きます!